前回
にて、定数変化法で定数係数かつ線形斉次の2階の常微分方程式を完全に解いた。
今回は線形非斉次の常微分方程式を解く際の一般的な方法である、特解を用いた方法について見ていく。
一般論
まず、次のような線形非斉次の常微分方程式を考える。
\begin{align}
\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n}f(x)}{dx^{n}}=h(x) \tag{1}\label{ippan1}
\end{align}
このとき、(\ref{ippan1})の非斉次項が0、すなわち\(h(x)=0\)の線形斉次の常微分方程式
\begin{align}
\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n}f(x)}{dx^{n}}=0 \tag{2}\label{ippan2}
\end{align}
の一般解を\(f_{0}(x)\)とし、元の線形非斉次の常微分方程式(\ref{ippan1})の特解を\(f_{\text{sp}}(x)\)としたとき、(\ref{ippan1})の一般解は\(f_{0}(x)\)と\(f_{\text{sp}}(x)\)の和、すなわち
\begin{align}
f(x)=f_{0}(x)+f_{\text{sp}}(x) \tag{3}\label{ippan3}
\end{align}
と表される。
以上である。
書いてみたらかなり呆気ないので、証明してみる。
(\ref{ippan1})の左辺に(\ref{ippan3})を代入すると、
\begin{align}
\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n}f(x)}{dx^{n}}&=\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n}}{dx^{n}}\{ f_{0}(x)+f_{\text{sp}}(x) \} \\
&=\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n} f_{0}(x) }{dx^{n}}+\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n} f_{\text{sp}}(x) }{dx^{n}} \tag{4}\label{ippan4}
\end{align}
となる。
(\ref{ippan4})の最右辺の第1項は、\(f_{0}(x)\)が(\ref{ippan2})の一般解だったことを思い出せばすぐに0とわかる。
そして第2項は、\(f_{\text{sp}}(x)\)が(\ref{ippan1})の特解だったことを思い出せば、第2項は(\ref{ippan1})の右辺に等しくなる。
よって
\begin{align}
\sum_{n=0}^{N}g_{n}(x)\frac{d^{n}f(x)}{dx^{n}}=0+h(x)=h(x) \tag{5}\label{ippan5}
\end{align}
となり、(\ref{ippan1})の右辺と一致するため、(\ref{ippan3})は(\ref{ippan1})の解であることがわかる。
また、\(f_{0}(x)\)が(\ref{ippan2})の一般解であるから、この\(f_{0}(x)\)の中に\(N\)個の任意定数が含まれているため、(\ref{ippan3})は(\ref{ippan1})の一般解である。
具体例
次のような線形非斉次の常微分方程式を考える。
\begin{align}
\frac{df(x)}{dx}+2f(x)=6 \tag{6}\label{rei6}
\end{align}
一般論と同様に考えてみる。
まず、線形斉次の常微分方程式
\begin{align}
\frac{df(x)}{dx}+2f(x)=0 \tag{7}\label{rei7}
\end{align}
の一般解\(f_{0}(x)\)だが、これは一回微分すると関数が元に戻る典型の微分方程式であることを思い出せば、\(C\)を任意定数として
\begin{align}
f_{0}(x)=Ce^{-2x} \tag{8}\label{rei8}
\end{align}
とすぐに求められると思う。
(すぐに求められなくとも、\(e^{\lambda x}\)を代入する方法を知っていればすぐに解ける。)
続いて(\ref{rei6})の特解\(f_{\text{sp}}(x)\)を求める。
(\ref{rei6})の形に着目すると、非斉次項と係数が全て定数であるため、\(x\)に関する多項式の解を想定すれば恒等式の形にもっていけそうである。
そこで、最高階の微分で定数になるように\(f_{\text{sp}}(x)=\alpha x+\beta\)とし、(\ref{rei6})に代入すると、
\begin{gather}
\frac{df_{\text{sp}}(x)}{dx}+2f_{\text{sp}}(x)=6 \\
\frac{d}{dx}(\alpha x+\beta)+2(\alpha x+\beta)=6 \\
\alpha+2(\alpha x+\beta)=6 \\
2\alpha x+\alpha+2\beta-6=0 \tag{9}\label{rei9}
\end{gather}
となる。
\(f_{\text{sp}}(x)\)はすべての\(x\)について(\ref{rei6})を満たさなければならないため、(\ref{rei9})は\(x\)に関する恒等式となる。
すなわち
\begin{align}
\begin{cases}2\alpha=0 \\ \alpha+2\beta-6=0 \end{cases}\tag{10}\label{rei10}
\end{align}
が成立し、これを解くと\(\alpha=0,\,\beta=3\)と求められる。
よって特解は\(f_{\text{sp}}(x)=3\)と求められる。
以上より、(\ref{rei6})の一般解は\(f_{0}(x)\)と\(f_{\text{sp}}(x)\)の和、すなわち
\begin{align}
f(x)=Ce^{-2x}+3 \tag{11}
\end{align}
と求められる。
物理での応用例
以前紹介した、鉛直ばね振り子の微分方程式を解く際にこの解法を用いている。
終わりに
この特解を使う方法は万能ツールであり、一般の線形非斉次の微分方程式に適用できる。
だからと言って\(f_{0}(x)\)と\(f_{\text{sp}}(x)\)の画一的な求め方があるわけではないが、初等物理で用いる微分方程式のパターン数はさほど多くないため、解いている内に解き方を覚えてしまうのが理想的だろう。
今回をもって、微分方程式の記事は一旦区切りをつけようと思う。
数学の記事は、次回からは行列に入ろうと考えている。
また物理の記事では、今回の特解を用いて微分方程式を解いていく問題の典型である強制振動を取り上げようと考えている。
END
※追記
「行列」の記事の執筆開始。





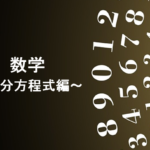

コメント