前回
にて、解を指数関数で置いた上で微分方程式を一般解を求める方法を見てきた。
しかし、上記の方法は完璧な方法ではなく、解が1つしか得られず一般解にこぎつけられない場合があることが判明した。
今回は、そういった場合に用いる解法である定数変化法について見ていく。
定数係数かつ線形斉次の二階の常微分方程式
前回、\(a,b,c\)を定数として、下記のような線形斉次の二階の常微分方程式を考えた。
\begin{align}
a\frac{d^{2}f(x)}{dx^{2}}+b\frac{df(x)}{dx}+cf(x)=0 \tag{1}\label{ippan1}
\end{align}
(\ref{ippan1})を解くには、\(f(x)=e^{\lambda x}\)とおいて代入し、\(\lambda\)に関する二次方程式を解けば良かった。
今回は、その二次方程式が重解を持つ場合を考える。
例えば\(\ell\)を定数として、
\begin{align}
\frac{d^{2}f(x)}{dx^{2}}-2\ell\frac{df(x)}{dx}+\ell^{2}f(x)=0 \tag{2}\label{ippan2}
\end{align}
の場合は、\(f(x)=e^{\lambda x}\)を代入しても\(\lambda=\ell\)しか求められず、任意定数を含む解としては
\begin{align}
f(x)=Ce^{\ell x} \tag{3}\label{ippan3}
\end{align}
しか得られない。ただし\(C\)を任意定数とした。
このままでは一般解にならない。
そこで、次のような解を考える。
\begin{align}
f(x)=C(x)e^{\ell x} \tag{4}\label{ippan4}
\end{align}
(\ref{ippan3})との違いがわかるだろうか。
ただの定数だった\(C\)を、形はわからないけど\(x\)に関する関数\(C(x)\)に置きかえたのである。
このように定数だったものを関数に変える手法であるため定数変化法という名がついている。
この(\ref{ippan4})を(\ref{ippan2})に代入して、合成関数の微分に留意して計算を進めていくと、
\begin{gather}
\frac{d^{2}}{dx^{2}}\{C(x)e^{\ell x}\} -2\ell\frac{d}{dx}\{C(x)e^{\ell x}\} +\ell^{2} C(x)e^{\ell x} =0 \\
e^{\ell x}\frac{d^{2}C(x)}{dx^{2}}+2\ell e^{\ell x}\frac{dC(c)}{dx}+\ell^{2} C(x)e^{\ell x}-2\ell e^{\ell x} \frac{dC(x)}{dx}-2\ell^{2} C(x)e^{\ell x} +\ell^{2} C(x)e^{\ell x} =0 \\
e^{\ell x}\frac{d^{2}}{dx^{2}}C(x)=0 \\
\frac{d^{2}}{dx^{2}}C(x)=0 \tag{5}\label{ippan5}
\end{gather}
となる。
(\ref{ippan5})は、\(C(x)\)を\(x\)で2回微分したら0になることを示しているため、\(C(x)\)は一次関数であることがわかる。
よって\(A,B\)を任意定数とすると(\ref{ippan5})の一般解は\(C(x)=Ax+B\)となるため、これを(\ref{ippan4})に代入すれば、(\ref{ippan2})の一般解
\begin{align}
f(x)=(Ax+B)e^{\ell x} \tag{6}\label{ippan6}
\end{align}
が得られる。
物理での使用例
以前、減衰振動を扱った際
に、下記の微分方程式を解いた。
\begin{align}
\frac{d^{2}z(t)}{dt^{2}}+2\gamma\frac{dz(t)}{dt}+\omega^{2}z(t)=0 \tag{7}\label{rei7}
\end{align}
この(\ref{rei7})に\(z(t)=e^{\lambda t}\)を代入して\(\lambda\)を求めると、
\begin{align}
\lambda=\begin{cases}
-\gamma\pm\sqrt{\gamma^{2}-\omega^{2}} \\
-\gamma\pm i\sqrt{\omega^{2}-\gamma^{2}}
\end{cases} \tag{8}\label{rei8}
\end{align}
の2つの解があり、上の解は粘性が強い場合、下の解は粘性が弱い場合の振動を示しているのだった。
前回はあえて扱わなかったのだが、当然\(\lambda\)のルートの中身が0になる場合も存在する。
ここでは(\ref{rei7})が重解になる場合を考えてみる。
ルートの中身が0、すなわち\(\gamma=\omega\)のときは\(\lambda=-\gamma\)となる。
このとき、(\ref{rei7})の解は\(C\)を任意定数として
\begin{align}
z(t)=Ce^{-\gamma t} \tag{9}\label{rei9}
\end{align}
が得られる。
ここで\(C \to C(t)\)として、(\ref{rei7})に代入して\(\gamma=\omega\)を利用して計算すると、
\begin{gather}
\frac{d^{2}}{dt^{2}}\left\{C(t)e^{-\gamma t}\right\}+2\gamma\frac{d}{dt} \left\{C(t)e^{-\gamma t}\right\} +\omega^{2}C(t)e^{-\gamma t} =0 \\
e^{-\gamma t}\frac{d^{2}C(t)}{dt^{2}}-2\gamma e^{-\gamma t}\frac{dC(t)}{dt}+\gamma^{2}C(t)e^{-\gamma t}+2\gamma e^{-\gamma t}\frac{dC(t)}{dt}-2\gamma^{2}C(t)e^{-\gamma t} +\omega^{2}C(t)e^{-\gamma t} =0 \\
e^{-\gamma t}\frac{d^{2}C(t)}{dt^{2}}=0 \\
\frac{d^{2}C(t)}{dt^{2}}=0
\end{gather}
となり、(\ref{ippan5})と全く同じ形の微分方程式が現れる。
よって\(A,B\)を複素任意定数として\(C(t)=At+B\)となるため、
\begin{align}
z(t)=(At+B)e^{-\gamma t} \tag{10}\label{rei10}
\end{align}
となり、(\ref{rei7})の一般解が得られた。
もともと\(z(t)=x(t)+iy(t)\)と定義していたことを思い出せば、\(C_{3},D_{3}\)を任意定数として
\begin{align}
x(t)=(C_{3}t+D_{3})e^{-\gamma t} \tag{11}\label{rei11}
\end{align}
となり、\(\gamma=\omega\)の場合でも運動を記述することができた。
細かい計算は省略するが、\(x(0)=x_{0},\, dx(t)/dt|_{t=0}=v_{0}\)とすると、(\ref{rei11})は
\begin{align}
x(t)=\{(\gamma x_{0}+v_{0})t+x_{0}\}e^{-\gamma t} \tag{12}\label{rei12}
\end{align}
となり、\(x_{0}=L>0,\,v_{0}=0\)のときは
\begin{align}
x(t)=L(\gamma t+1)e^{-\gamma t} \tag{13}\label{rei13}
\end{align}
となる。
この(\ref{rei13})をグラフにすると、形そのものは\(\gamma>\omega\)の場合と同じで、初期位置から振動せずに自然長に落ち着くように変化する。
しかし、自然長へ減衰する速さは(\ref{rei13})の場合が最も速い。
この\(\gamma=\omega\)のときの減衰を臨界減衰と呼ぶ。
終わりに
前回と合わせて、定数係数かつ線形斉次の2階の常微分方程式は完璧に解けるようになった。
あと考えるべきは、ここに非斉次項がプラスされた場合である。
例えば、先ほど取りあげた減衰振動に重力が加わった場合。
もし復元力の項、(\ref{rei7})における\( \omega^{2}z(t) \)の項がなければ、(\ref{rei7})は1階の常微分方程式に書き換えられて変数分離の方法が使えるが、復元力の項が残っていると変数分離の方法は使えない。
次回は、そのような線形非斉次の常微分方程式に一般的に適用できる解法を紹介する。
END
※追記
線形非斉次の常微分方程式の一般的な解法について執筆。




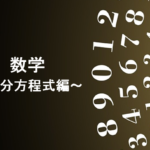
コメント